Top Page > Online Resources > housing in China / 中国城鎮住宅建設の制度改革
中国城鎮住宅建設の制度改革:市場化が進む世界最大の住宅市場
(株)三菱総合研究所
政策研究部 寺村孝太郎
はじめに
90年代は住宅制度の改革期にあたり、中国の住宅需給を巡る環境は大きく変貌を遂げようとしている。中国の住宅投資額は1993年で2,722億元、GDPの7.8%、全社会固定資本投資額(固定資本形成)の22%を占めている。また1996年における住宅総建設量は、農村および城鎮(都市と町)を合せた全国で12億2,188万?u(竣工建築面積)、うち城鎮住宅建設だけでも3億9,434万?u。日本の新設着工住宅床面積が同年1億5,790万?u(過去最高を記録)であることと比べると、人口一人当りでみて、現在の日本の住宅建築ラッシュと同じ状況が中国で起こっている。
他方、アジア金融危機に伴う東南アジア諸国の通貨切り下げと経済スローダウンにより、これまで経済成長を牽引してきた輸出や外資導入が減速することは避けられず、今後、8%の安定的な経済成長率を維持するためには、相当の公共工事・企業設備投資および住宅建設など国内需要を拡大する必要がある。都市部の住宅建設投資は、第9次5ヶ年計画「九五」における重点項目とされており、内需の安定拡大のため力が注がれるとみられる。
住宅建設でメリットを受けるのは、直接、建設業だけではない。住宅建材、住宅部品、住宅設備機器、室内装飾品、家電製品、家具、楽器、また上下水道、電気ガスなどの工事とエネルギー使用など住宅新設に伴って喚起される需要の裾野は極めて広い。さらに、ハードウェアのみならず、住宅情報提供や施設維持管理などのサービス技術提供を含めると、住宅関連市場は極めて大きいものである。
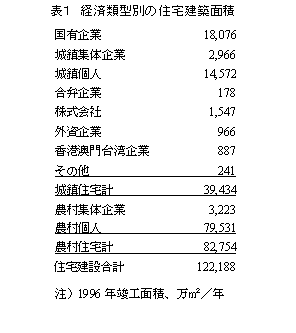
中国政府は住宅建設の生産波及効果を国内需要振興と産業育成の面から大いに期待している。これはまた、日本の企業にとっても広範囲にわたりビジネスチャンスに繋がる動きとして、新たな関心を呼ぶ問題といえる。
2000年には一世帯一住宅がほぼ達成され、さらに2010年までに「一人一室」の居住水準目標が掲げられており、来世紀初頭の10年は、「量から質の向上へ」を実現する期間とみなすことができよう。今回のレポートでは、さらに拡大が期待されている中国都市部の住宅建設に注目し、以下について分析展望したい。
・住宅投資ルートと住宅供給の現状
・中国政府の2010年を睨んだ住宅供給政策
・進みつつある住宅改革の内容とその含意
・2010年までの城鎮住宅建設規模
1.住宅投資ルートと住宅供給の現状
都市では、これまで個人が住宅を建築することは許されておらず、企業や機関がそれぞれの従業員のために住宅を建設しそれを貸与してきた。都市の国営企業の従業員はすべて住宅を給与され、低家賃の住宅保障がなされている。日本でいえば国家公務員すべてが公務員住宅に住むと考えればいいが、中国においては都市の就業者1億8,600万人のうち、国営企業の従業員は1億1,480万人で全体の62%を占めている。日本の就業者の2倍に当たる個人に対して、政府あるいは国営企業が住宅を給付していることになる。国有企業が抱える巨額の赤字の一因は、多くの余剰従業員と彼らに対する低家賃の住宅保障にある。
図1 城鎮住宅建築面積の推移
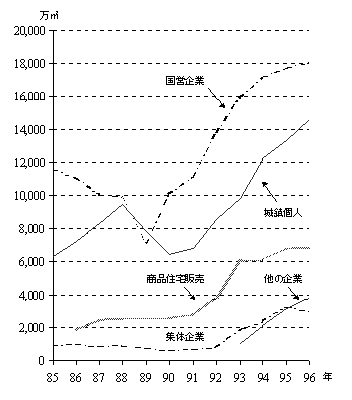
中国の住宅需給構造は日本とはかなり異なるため、やや微に入る言及となるが、まず中国における住宅投資主体・住宅投資ルートを概観しておこう。1978年まで都市の住宅建設は主として国家基本建設計画を通じて行われていた。改革解放以降、住宅建設の投資ルートが広がり、現在では次の6つの分野で行われている。
1) 国有企業の資金源による住宅建設
国有企業の住宅投資は、基本建設投資のうち国家財政予算による建設資金(予算内資金)と、中央政府の各部門および地方政府と各国有企業が自ら調達した資金で行う建設資金(予算外資金)の2つを資金源として行われている。予算内資金による割合は低減してきている。従業員住宅建設資金については、原則、企業の従業員福利基金や従業員奨励基金を利用するものとされており、予算外資金によるものが80%以上を占めるようになってきている。
また更新改造資金の一部を従業員住宅の再建と維持管理に用いることができる。
1985年においては、城鎮住宅建設の62%が国営企業による住宅投資であったが、城鎮個人やその他の企業の住宅建設が急激に増加して、1996年にはその割合が46%にまで低下してきている。
2) 集体企業の資金源による住宅建設
集団所有制単位 注)の固定資本投資は国家の基本建設投資には含まれておらず、集体経済の従業員住宅建設資金は、各企業の納税後利潤留保および積立金により確保するものとされている。93年に分類区分が変更され、96年では城鎮住宅建設のうち7.5%を占めている。
注)県政府所管以上の企業は国有企業とされ、郷以下の町村営企業や農村における共同出資企業などが集体経済(集団所有制単位)と分類されている。
3)その他の企業の住宅建設
合弁企業・株式会社・外資企業・香港澳門台湾からの投資企業・その他(主として個人経営)が建設・購入する住宅は、94年以降急速に増加して来ており、1996年では3,820万?uで城鎮住宅建設の9.7%を占めるまでになっている。
4) 個人投資による住宅建設
近年の所得向上により、個人資金による住宅購入が増加している。1996年で個人住宅建設は城鎮住宅の37%を占めるに至り、今後、国営企業による住宅供給の役割が低下するにつれて、その比重はますます大きくなるとみられる。これらは自己資金によるもののほか、後述する「住宅協同組合方式」や政府の「安居住宅事業」による住宅取得が多くを占めるようになってきている。住宅融資も徐々に整備されてきており、資金調達が困難な住宅建設に対しては、個人の資金を基本としつつも、補助的に地区の政府あるいは従業員が所属する企業の援助、一定額の無利子貸し付けを利用できるようになってきたことが、増加の要因である。
ただし個人による住宅建設にはなお、次のような様々な制約が残っている。
・企業が個人の住宅建築に対する経済的援助を行うばあい、補助する金額が一般に住宅コストの20%を超えることはできないとされている。
・購入された住宅建物は個人の所有物となるが、土地所有は認められておらず、個人はただ土地の使用権を有するだけである。住宅用地は政府がまとめて収用し、統一的に住宅区画用地を企画設計して造成を行い、土地の徴用費等は政府と企業が負担している。個人は土地の使用費(税)を納めなければならないが、これらの収用・造成費を賄える額にはなっていない。
・さらに「城鎮個人建造住宅管理弁法」1983年によれば、都市の個人住宅建設は、一人当り建築面積が一般に20?uを超えることはできない。また、およそ都市に正式の戸籍を持ち、住宅に確かに困難のある居住民と従業員はみな住宅の建設を申請できるが、夫婦一方の戸籍が農村にあるものは、一般に都市での住宅建設を申請できないとされている。
5) 住宅協同組合方式による住宅建設
政府が組織した住宅組合は、広く一般に組合員(住宅購入者)を募集し、住宅販売および一連の系統だった組合員規則、組合住宅の補修管理規定を定めて、政府が住宅組合組織の運営と管理を行うものである。住宅購入は分割払で、分譲の団地開発といったものであり、幼稚園・小学校や商業施設などが配置されされているものもある。
企業による従業員住宅組合は、組合住宅を企業が直接管理し、組合員は主に企業の従業員であるという形態。政府が住宅建設計画を示して住宅組合に参加する企業を募る形態もある。
政府あるいは企業によるもののいずれとも、住宅協同組合に参加する個人が住宅資金を負担し、政府あるいは所属企業が一部を補助する。個人の住宅資金に対しては、低利担保貸付が適用され、まず住宅価格の30%を納めた後、残額を3〜10年に分けて完済する。
これら住宅協同組合による住宅建設は、その一部は国営企業あるいは集体企業の住宅建設に、その他は個人の住宅投資に含まれているとみられるが、統計では明示されていない。
6)商品化住宅(商品房、売り出し住宅)
商品化住宅は、専業化した不動産開発公司が総合開発建設を行い、竣工後に販売あるいは賃貸される住宅をいう。1980年頃からいくつかの都市で始まった商品住宅は、1986年の1,835万?uから1996年には6,898万?uの販売量に達している。商品化住宅は、当初、主に国営企業や集団企業など企業へ売られてきたが、徐々に個人購入が増えてきている。統計上、各種主体の住宅建設投資の中に含まれているため定かではないが、個人が購入した商品住宅は3,667万?uであり(1996年)、これは商品住宅販売の53%、城鎮個人住宅投資の25%を占めるに至っている。
商品住宅の全国平均価格は96年で1,604元/?uであるが、外国人向けの高級住宅から一般勤労者向けまで幅広くあり、また地域格差も極めて大きく北京や上海の平均価格はそれぞれ3,869元/?u、2,968元/?uと2倍以上の開きがある。城鎮と工鉱業区における個人住宅建設の平均建築単価が全国平均で388元/?u、北京・上海が530元/?uに比べると商品住宅は3倍から4倍高い。
中国では各地の経済状況や人々の住宅に対する観念が異なるため、中央政府が全国共通の標準的な住宅制度モデルを提示して各地に実行させることをせず、各地での経験を積み重ね、各地の事情に応じた個別政策を奨励している。以上のように計画経済のなごりが多く残る住宅分野でも改革が模索されており、国家財政や企業の資金調達から個人による住宅投資へ、また専業の住宅ディベロッパーによる住宅建設への転換が進んでいる。
2.中国政府の2010年を睨んだ住宅供給政策
今後、中国の住宅供給制度がどのような変貌を遂げるか。第2回国連住宅会議(HABITAT?U)で提出された中国人民共和国人類住区発展報告(1996年)に、次のような2010年住宅供給目標と政策展開が提示されており、これから政府の意図と将来の姿を明確に読み取れる。
2.1 住宅供給目標
2000年までの目標と住宅建設量
1996年〜2000年: 都市 12億?u(年平均2.4億?u)
農村 28億?u(年平均5.6億?u)
都市のすべての世帯に1世帯1住居を確保し、その70%は基礎的設備が整った住宅とする。一人当り居住面積9?u(同、使用面積は12?u)を実現する。
建築床面積で示すと、3人家族で一世帯当り54?uと考えられる。因みに1996年における都市の一人当り平均居住面積は8.5?u、一世帯当り51?uである。
2010年までの目標と住宅建設量
2001年〜2010年: 都市 33億?u(年平均3.35億?u)
農村 50億?u(年平均5億?u)
すべての都市世帯が基礎的な設備が整った住宅に住み、一人当り使用面積は18?u、一人一室を実現する。
同じ推定をすると3人世帯で81?uとなり、10年で住居面積を1.5倍にする目標とみられる。対象地域がことなるため一概に比較できないが、日本で一世帯一住宅が実現した昭和43年当時、三大都市圏の平均住宅面積は58?u、その10年後の昭和53年で70?u弱、平成5年の住宅統計調査では持ち家借家を合せた平均で78?uとなっている。
なお、居住面積は居間、応接室、寝室など人が寝起きしくつろぐ部屋の面積。使用面積は、居間・寝室・応接室に玄関、廊下、納戸、台所、洗面所トイレなどを加えた正味面積、建築面積は外壁を含む総床面積である。
2.2 目標達成のための政策内容
1)市場原理に基づく新しい住宅供給制度を段階的に整備する。現行の住宅制度は福祉的手当てとしての無負担の住宅給与および低家賃となっているが、今後は、住宅建設コストと受け取るサービスへの対価が反映された供給制度へ段階的に移行する。
2)住宅投資に関し、その資金源を安定的なものとするため、中央と地方政府・企業および個人が適切に負担を分かち合う住宅資金融資システムを確立する。
・ 雇用主と従業員の双方から一定率の資金を集める貯蓄基金の中央機関を設立する。この基金は個人の住宅購入・建設あるいは維持管理に対し融資を行う。貯蓄基金の中央機関の設立とその充実により、個人からの住宅資金を次第に増加させる。
・ 現存する銀行の役割も活用しつつ、住宅建設・住宅保険に関して融資事業を積極的に実施する。特に、一般的な住宅を対象として、個人の住宅購入資金に特化した住宅銀行の段階的な設立に取り組む。また個人の住宅購入・建設資金のための長期抵当権融資を充実する。抵当融資への返済金は個人所得税が免除され、融資期間は現行の10年から15年に段階的に延長される予定である。
・ 中低所得者や住宅協同組合の加入者に対し、自己資金調達による住宅取得を促す施策を講じ、個人の組織的な住宅建設への取り組みを促進する。
3)社会主義市場経済に合致した住宅価格の決定
・ 開発事業者によって建設された商品住宅は、政府の管理と指導の下に、需要と供給のバランスから市場原理によって決まる価格で取り引きされる。
・ 中央政府および地方政府からの助成を受けて建設された商品住宅は、適正な利益の範囲内で政府が決定した価格によって取り引きされる。
・ 政府が直接供給する、あるいは政府の援助によって建設する一般的な住宅(政府の基準にしたがって建設された住宅)、個人が住宅協同組合制度によって建設する住宅は、建設原価で取り引きされる。
・ 現有する公共住宅の個人への払い下げは、政府の住宅制度改革指針にしたがって決定される価格による。
4)住宅開発施策に応じて異なる土地提供価格の設定
・ 実用的かつ低コストの住宅、個人住宅あるいは協同組合方式で建設される住宅に対しては、土地は政府により無料で提供される。
・ 適正利益で販売される一般的な住宅に対して、土地は政府が取り決めた特価で提供される。
・ 市場価格で販売される商品住宅は、入札・競売あるいは契約に基づく価格で提供される。
5)住宅困窮世帯に対し優先的に住宅支援「解困工程」を行う。
住宅困窮戸とは、都市の居住民世帯の中で、家がなく倉庫や屋根裏、簡易バラックに住んでいる世帯、3世代が一室に住んでいる、あるいは2世帯が一室に同居している不便世帯、一人当り居住面積が2?u足らず(特別困窮戸)と4?u足らずの世帯(困窮戸)を差す。解困工程の事業内容は、各地の政府が調査登録に基づき、普通標準の住宅を政府が直接総合開発、あるいは開発公司(ディベロッパー)が建設した商品化住宅を少しの利益で政府に供給して、政府が低利益・低コスト・低価格の住宅を住宅困窮戸に販売または賃貸する。解困工程は強い行政手段の色彩をもっている。
6)中低所得世帯への社会保障として実用的かつ低コストの住宅供給(後述する安居住宅事業)を行うとともに、高所得世帯を対象とした商品住宅の供給を進める。
3. 進みつつある住宅改革の内容とその含意
上記の住宅供給政策は、これまでの住宅支給、低家賃、高補助という福祉型の住宅分配制度を改め、住宅の購入主体を企業から個人へ転換し、住宅の私有化を進めようとするものである。すなわち住宅の所有権所得あるいは応分の受益負担を負う使用権へ転換することによって、住宅を商品として消費市場に組み入れ、住宅の資金調達・建設・販売流通・管理を市場化することが、制度改革の長期的なねらいといえる。
1)公有住宅の家賃引き上げ
日本の賃貸住宅における家賃には、通常、地代・土地造成費・建物減価償却費・建物維持費・管理費および税・利潤が含まれるが、中国の家賃「房租」は管理費程度のコスト設定になっており、住宅建設コストを反映した住宅費となっていない。城鎮世帯の一人当り平均年間消費支出をみると、房租額は1981年6.36元、1985年6.48元、1990年9.43元であり、この期間の物価上昇を勘案すると極めて割安な家賃となっており、それぞれ平均年収入に対してわずか1.27%、0.86%、0.62%程度のものに過ぎない。
城鎮個人住宅の建築単価と比較すると、85年では78元/?u、90年153元/?uであり、一世帯当り世帯人数が3.5人とすると当時一戸当り5,000元の住宅に対して年間の世帯当り家賃支払が33元ということになる。これには土地の収容造成費などは含まれておらず、総建設コストとの差額はすべて、国や国営企業等の補助=負担となるわけで、資金の行き詰まりが目に見えている。
1987年以降、これまで各都市で公有住宅の家賃値上げが行われ、1994年では全国平均で28.79元と85年に比べ4.4倍に上昇してきている。現在は急激な負担増を緩和するため、公有住宅の家賃標準を引き上げると同時に、公有住宅に住む居住者に相応の住宅補助金が支給されている。
今後、家賃は投資回収ができるレベルまで、つまり減価償却費・補修費・管理費・投資利息・家屋不動産税を含むコスト家賃のレベルに引き上げられるものと予想される。
2)公有住宅の払い下げ
世帯が現在住んでいる公共(中古)住宅に格安の値段と優遇条件をつけて、政府が現入居世帯に即時払いで売り出し、直接資金を回収しようとするものである。これは、政府あるいは国有企業の金利負担を軽減するとともに、またその資金を利用して新たに住宅を必要とする世帯の住宅建設に投入することができ、資金回収方法としては手っ取り早く、即効性がある。
さらに家賃の切り上げにせよ、住宅の払い下げにせよ、これまでの高福祉型住宅供給は先々縮減されるというアナウンスメントは、人々の従来の住宅観念を改め、住宅の分配を待つ人が自分で住宅を購入することを考えるようになる効果をもっている。
3)住宅積立金
従業員が毎月の賃金の一定率を積み立て、同時に所属企業も従業員のために同額を貯え、従業員の名義で長期に貯蓄して今後の住宅購入に利用される。公共積立金制度は、立法を以って市政府が組織する住宅積立てへの参加を義務づけようというものである。これはまた、従業員が定年時あるいは退職時に公共積立金を一括して引き出すことができ、養老保険としての性格も持つものである。
住宅積立金は、政府からみると、住宅取得が行使される時差を利用して、積立て残高から多額の住宅建設資金を調達することができる。またこれを利用する従業員個人には、所属企業から住宅保障金を預金として受け取ることができ、積み立てが進みこれにより取得した住宅は自分の所有物となるメリットがある。
日本や欧米では一般的になっている住宅金融制度のひとつであるが、公共積立金制度は、上昇する個人所得を消費に向かわせるのではなく、預金として貯蓄させるという政府のねらいがある。住宅建設を進めると同時に、貯蓄を促すことでインフレを抑制する。また貯蓄を増やすことで住宅投資資金の確保も狙ったものといえる。
経済主体別の金融資産残高をみてみると、1995年の総資産5兆4,000億元のうち41%の2兆1900億元が城鎮の個人預金貯蓄であり、企業の預貯金1兆4500億元の1.5倍の群を抜いた規模となっている。1985年では企業預貯金が城鎮個人預貯金の2倍であったものが、国営企業の経営不振もあって、この10年間で逆転し、金融資産の保有構成が大きく変化した。城鎮個人預貯金は95年GDPの38%を占めるに至っている。
財政難の中にあって、個人預貯金は投資の資金源でもあり、また有効需要を操作し物価を制御する対象ともなっている。インフレが激しかった1988年や1993年では預金離れを防ぐため、政府は利子補填を行ったことから見ても、その重要性を窺い知ることができる。住宅金融制度は、このように一面、貯蓄誘導の側面をもっており、物価上昇の抑制と対GDP40%という高い貯蓄率を維持するための政策手段とも見なしうるものでもある。
表2 中国における住宅の市場経済化
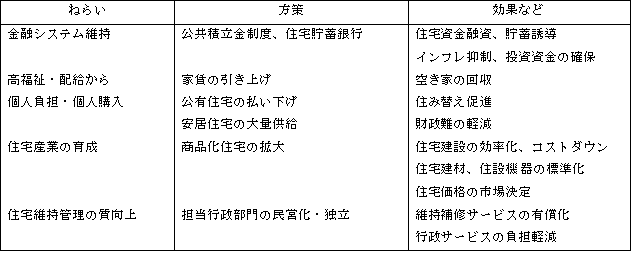
4)安居住宅事業の推進
都市の中低所得世帯および住宅困窮世帯に対し、実用的かつ低コストの住宅「安居住宅」を供給する事業が1995年から進められている。これは、前述の解困工程や「経済適用住宅」建設など都市の中低所得の従業員住宅問題を解決するために行われる様々な計画を総称したものと広義に理解されている。
「経済適用住宅」は、社会保障性を持つ商品化住宅である。社会保障住宅開発機構が住宅の建設販売に当たるが、一般の不動産開発公司とは異なり、独立法人ではあるが政府の厳格な規制を受け、利益を抑え社会一般の中低所得世帯に安価な住宅を供給する機構である。住宅提供価格は建設コストと市場価格の中間に設定てれている。
経済適用住宅を建設する建設業者は、販売価格を制限され、また販売・賃貸の対象者を政府によって審査されるものの、土地の供給、開発や税制面での一定の優遇が与えられる。このような中低所得者向けの低コスト住宅を大量に供給することにより、住宅産業の育成と住宅建設コストの低減を図ろうとするものである。
5)住宅維持管理体制の改革
現行の不動産管理は、ほとんど行政機関や企業の事業部門が担っており、行政経費や企業の事業費に頼って事業を維持していて、その業務は行政的な行為または無償に近いサービスとなっている。私有住宅ではなく借り物となると保全が悪い。これらの不動産管理部門が住宅を補修してきたが、資金が乏しいため住宅の破損が甚だしくひどいものであった。
これは、今後進む個人の住宅私有化に対しては馴染まない機構と制度であり、有償管理サービスを提供し、自主経営で自らが利益責任を負う独立企業に生まれ変わると予想される。
より広い住宅でさらにゆとりのある生活をというニーズは潜在的に強く、住宅制度改革は試行錯誤を繰り返しつつも、住宅需要者に「住宅は自らの資金で購入するもの」との社会通念が浸透するにつれて、大きく動き出すとみられる。
他方、商品化住宅の過剰供給が問題になる側面もある。これは高価な外国人向け高級マンションの売れ残りや主要な買い手である国有企業の収支が悪化しているなどの理由もあるが、不動産開発公司が供給する住宅価格が高いこと(不動産ブームのときは50〜100%の利益をかせでいた事例もある)、また需給がルースになっても値を下げないこと、あるいは開発された住宅団地の立地が悪いことなど様々な原因が挙げられる。
このような供給者側の行動も、市場調査やプロジェクト評価のノウハウが蓄積されるに伴い、また入札や市場による価格決定を通じて淘汰され、市場化が進むと思われる。
4. 2010年までの城鎮住宅建設規模
城鎮世帯の年収は急速に伸びており、貯蓄を進めながらも、96年でカラーテレビ93%・洗濯機90%・冷蔵庫70%の普及率となり耐久消費財はほとんど行き渡っている。さらに大都市部では教育費等サービス支出も増加している。家賃負担額が極めて小さく、また医療等も厚い社会保障が受けられる下で、消費生活は相当満たされたレベルに到達している。
図2 城鎮家庭の年収、家電普及率
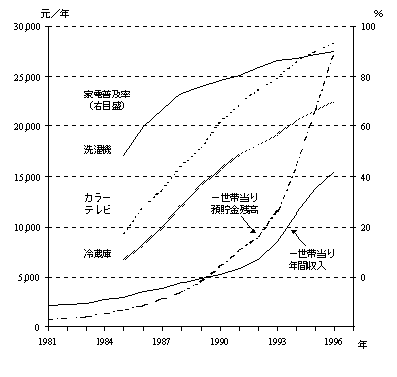
平均的な家庭の住宅取得力はどうであろうか。城鎮における一世帯当りの全国平均年収入は14,000元に達しており、また銀行預貯金残高も一世帯当り2万元を保有するに至っている。大都市中心部は無理としても5万元/戸(たとえば1,000元/?u×50?u)の住宅を購入するとすると、頭金40%として当初2万元、10年返済で年3,000元、年収の20%を返済に当てれば手が届かないものでもない。今後、住宅建設コストが下がり、また長期の抵当融資制度が導入されれば平均的な世帯でも住宅購入が可能な取得能力を有する段階にきている。
支払能力があるという前提で、新設住宅建設はどれほどの規模が見込まれるか。城鎮人口は、1995年で3億5,000万人強であるが、行政区分の変更で都市に格上げされる地域が増えるため、2000年には4億5,000万人、2010には6億3000万人となり、都市人口は総人口の45%に達すると予想されている。城鎮の家庭戸戸数は95年1億900万戸から、2000年で1億5000万戸、2010年は2億1,000戸になるとみられる。また20〜29歳人口も2000年では若干減少するものの、2010年には95年の人口を上回る。
これを基に試算すると、城鎮住宅建設は2000年までの5年間年平均で3億8,000万?u、2010年までの年平均建設量は4億8,000万?uになるとみられる。
国際協力事業団の日中技術協力「中国住宅新技術研究・人材育成センター・プロジェクト」の中で、筆者は中国建設部建築技術研究院との情報交換を進めてきた。本レポートは、この共同研究の一部をまとめたものである。
新設住宅着工戸数は、日本で150万戸、アメリカ130万戸、西ドイツ60万戸、フランス30万戸、イギリス20万戸であり、先進国の中でも住宅竣工面積が2億?uを超える国はない。中国では、上記のように城鎮(都市と町)のみで2010年には5憶?uの住宅建設が見込まれる。
これまで国と企業からの配給で埋もれていた住宅建設は、市場化とより質の高い住宅供給が進むことに伴って、耐久消費財・住設機器・室内装飾などの需要を喚起し、次なる消費ブームと巨大な住宅関連自由市場を生み出すものと期待される。
(以上)
Send mail to Contact@teramura.com with questions or comments about this web site
teramura research lab. Copyright (C) 2002-2016 all rights reserved.