Top Page > Online Resources > Energy & Environment / 中国の環境保全・省エネルギーに目を向けるとき
中国の環境保全・省エネルギーに目を向けるとき
寺村孝太郎
1.エネルギー逼迫がもたらした事件
大規模な炭田火災が発生しており、消火に100年を要するという。中国新疆ウイグル自治区で、放置された数十箇所の炭田で自然発火による火災が相次いでいる。石炭を掘り出したあとの炭田は、空気に触れたまま放置しておくと、石炭層から出る揮発ガスが発火する。1990年代、めざましい経済成長の中で急増するエネルギー需要を石炭で賄うため、炭田の乱開発が行われたことが、この背景にある。
延焼規模は100キロ?u以上にも及び、また地下の石炭層自体が燃えているという事実もあって、消火には途方もない時間と資金が必要である。この炭田火災によって焼失する石炭は年間1000万トンを下らないと推定されている。これは、日本の年間石炭輸入量の10%、日本の電力業が需要する年間受入れ量の30%に相当する。消火作業の人員投入と資金、資源の喪失ばかりでなく、二酸化炭素放出による環境汚染が深刻であり、「経済・資源・環境」の三重の面からコストが課せられた問題といえる。
100年の信憑性がどうあれ、エネルギー供給が需要に追い付かない逼迫状況がもたらした事件であり、急激な経済発展とそれがもたらす影響に少なからず危惧を抱かせるものである。周知のとおり、人口・食糧・エネルギーは中国の長期的潜在的課題であるが、これらに加えて、環境問題が重大な課題となってきていることを表している。以下では、中国のエネルギー利用が環境に対して負荷をかけ易い構造になっていること、またこれが今後15年にわたってほぼ相似形で拡大することを紹介するとともに、中国に向けての環境保全技術の提供や資金供与に対する国際協力の必要性を、改めて訴えたい。
2.2010年に向けた中国の成長目標
世界銀行は貸付対象国を所得水準に応じて4つのグループに分けている。一人当たりGNP(1992年)が675ドル以下の低所得国、676〜2,695ドルの低位中所得国、2,696〜8,355ドルまでの上位中所得国、8,356ドル以上が高所得国である。中国は470ドル(1992年)で、ギニア ・モーリタニア ・ジンバブエ ・エジプトと同分類の低所得国に位置付けされている。因みにフィリピン ・ペルー ・ルーマニア ・コロンビア ・タイ ・ポーランド ・イラン・ロシア ・チリなどが低位中所得国、ブラジル ・メキシコ ・韓国 ・サウジアラビアなどは上位中所得国である。
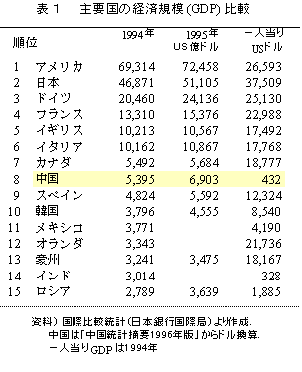
(1)射程に入ってきた先進国へのキャッチアップ
ドル建て一人当たりGDPの大きさでみる限り中国はまだ開発途上国の水準とみなされるが、この指標で中国の経済力を測ると、中国の実力と躍動を見誤る。1994年、中国の名目GDPは世界第8位、1995年はカナダを抜いて第7位となった(表1)。G7並みの経済規模を有するに至ったわけだが、5年後には名目GDPでほぼイギリス・イタリアに並ぶだろう。中国経済の将来を展望した報告はいずれも、21世紀初頭、中国が主要先進諸国と並ぶ経済大国になるとみている。ついに経済力で先進諸国と肩を並べる経済規模に到達しうる見通しがつき、欧州先進国へのキャッチアップが射程に入ってきた。中国経済はようやく成長軌道に乗ったといってよい。
中国の歴代指導者には、「先進諸国に追い付き、追い越せ」という強い願望がある。中華人民共和国の建国以来、毛沢東・周恩来は先進国に追いつく構想を夢見てきた。登小平体制が確立されてから現実的目標に転換し、胡耀邦が「今世紀末までにGNP4倍増」(1982年)を、また趙紫陽が三段階構想を提起した(1987年)。1990年の経済規模を80年の2倍に、2000年までに4倍にする倍増計画で、新中国樹立から100年に当たる21世紀半ば頃までに一人当たりGNPを中進国並みに引き上げるというものである。
2倍増計画は90年を待たず1988年に達成された。同年、内陸部の発展の機動力とするため沿海地区の急速な発展を優先する「沿海地区経済発展戦略」が提唱され、いわゆる先富論による経済発展が動きはじめた。さらに1992年、登小平の南方沿海地区視察での発言が空前の投資ブームを呼び、バブル経済期(1992〜1994年)をもたらしたことは周知のとおりである。第8次5ヶ年計画の期間に当たる1991〜95年の平均実質成長率は12.5%であり、金融ブーム後の経済調整でスローダウンした先進諸国(OECD諸国平均)の同期間が1.6%であった状況と対照的であった。これによって先の4倍増計画は、5年も繰り上げ達成され、1995年に80年のGNPの4.3倍となった。
(2)次の目標は一人当たりGNPの引き上げ
1996年から始まる第9次5ヶ年計画では年率8%の経済成長が計画されており、インフレを抑制した安定成長へと経済調整を進めてられている。毎年1300万人ずつ人口が増えつづけ、来世紀には13億人を抱えることになる中国にとって、経済成長はmustである。経済規模ではG7並みの大きさに成長したものの、一人当たりGNPは未だ日本の80分の1しかなく、中国国内の所得格差は大きい。1994年で一人当たり所得が最も高い上海市は14,542元/人、他方最も低い貴州省では1,507元/人であり、その差は10倍程ある。また内陸部は全国平均の半分の所得であり、沿海部と内陸地域との所得格差が問題視されている。さらに個人別にみると所得格差は著しく、年収が530元(日本円にして約1万円)以下の絶対貧困層が6,500万人にも及ぶと言われている。
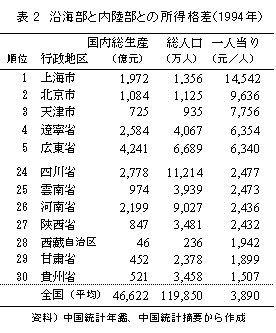
これまでの量的拡大から、地域格差を是正しながら一人当たり所得を引き上げていく政策転換に迫られている。2010年に向けた次の目標は「一人当たりGDPを引き上げる」ことである。江沢民は、2010年長期発展目標において、2000年の一人当たりGNPを1980年の4倍(1,200USドル/人)に引き上げ、さらに2010年ではGNP総額を2000年の倍にするという目標を掲げている。
倍増計画はまだ当分続きそうである。難題を抱えながらも、巨大な人口圧力が否が応でも経済成長を迫る構造が内蔵されている。経済成長がmustであること、キャッチアップ意識が底辺にあることから、さらに国有企業の改革、価格改革、食糧増産、内陸部と沿海部との地域格差問題、絶対貧困層の解消など数々の難題を抱えながら、急激な経済発展を進める中では、どうしても「成長第一、環境保全は第二」に陥り易い。さらに、以下のエネルギー利用構造と照らし合せて考えると、環境保全の面で懸念すべき危うい条件が揃っていると言わざるをえない。
3.石炭に偏重するエネルギー構造
中国の一次エネルギー消費量(1993年)は石油換算で7億888万トン、世界消費量合計の9.1%を占めている。アメリカ19億5258万トン(25.2%)・ロシア共和国の7億1753万トン(9.2%)に次いで世界第3位である。日本が中国に次いで第4位、4億1811万トン(5.4%)を消費している (いずれも国連のEnergy Statistics Yearbook 1993による)。
中国のエネルギー需給構造の最大の特徴は、図1をみれば一目瞭然だが、エネルギー利用が石炭(固体燃料Solid Fuels)に極めて大きく依存していることである。
図 1 世界主要国の一次エネルギー消費(燃料別構成比)
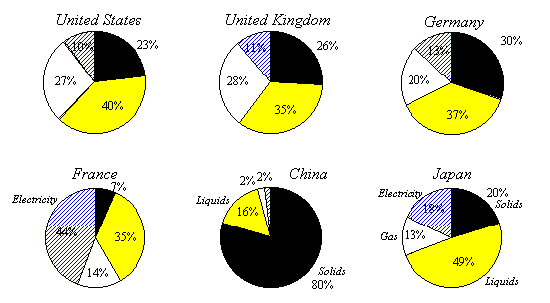
資料)Energy Statistics Yearbook 1993: United Nationsより作成
世界平均では30%弱であり、固体燃料依存率が80%というのは主要国の中で際立って高い。石炭の生産及び消費は世界で最も多く、世界の約3割を占めている(表3)。
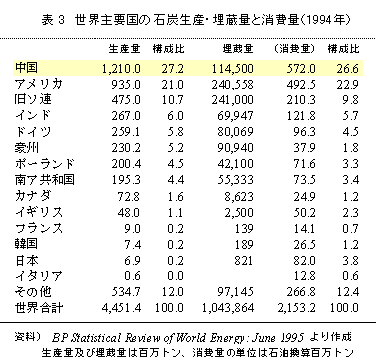
このような石炭依存は、埋蔵量が豊富であることが第一の理由だが、石炭に代わるだけの石油や天然ガスの増産能力が見込めないこと、これまでエネルギー多様化政策に積極的でなかったこと、また石炭価格が極めて安価に設定されていることが、その背景にある。
2010年まで中国の一次エネルギー消費は年率4%程度で増加していくとみられている。この年率4%は20年で2倍強になる増加スピードである。中国の一人当たりエネルギー消費は年間603kg /人(石油換算、1993年)であり、日本の3,357kgに比べて5分の1、アメリカ7,570kgに対しては12分の1に過ぎない(いずれも数値には薪などの非商業用エネルギーを含まない)。人々が豊かな消費生活を求める限りエネルギー消費の増加は避けて通れない。今後の経済成長に伴って、中国のエネルギー増は世界のエネルギー需要を押し上げる強い圧力になる。
問題は、増大するエネルギー需要を賄う供給構造であり、石炭偏重が大きく変わりそうもない点である。まず、第二のエネルギー源である石油供給力からみてみる。
中国の石油生産は、約40%を大慶油田に、20%を勝利油田、10%を遼河油田に依存している。大慶の生産能力は低下してきており、その他の油田の増産能力もさほど期待できない。タリム盆地の石油開発が期待されているものの、安定供給が見込めるだけの埋蔵量が未だ確認されておらず、遠隔地にあるため油田開発とパイプライン敷設に莫大な資金を要する。1994年の国内石油生産1億4608万トンに対して、将来の生産増は年率2%程度を見込めるに過ぎず、2010年で2億トンの供給がせいぜいとみられている。たとえタリムの開発が成功したとしても5000万トンの供給増で、総供給2億5000万トンが上限である。
他方、生産拡大やモータリゼーションの進展、都市型生活の浸透によって、今後石油需要が増大していくことは必死で、石油需要は年率5%で伸びると予想されている。需要が供給を超えるため、2010年では1億トン以上の石油純輸入が必要となる。中国が恒常的に石油の純輸入国になるのは確実である。(現時点においても1993年から輸入が輸出を上回り、1994年では輸入が2903万トン、輸出は2380万トンで、523万トンの入超となっている。)天然ガスの供給は年率8%で伸び、一次エネルギー供給のシェアが4%となると思われるが、これにしても巨大な需要を賄うに足るエネルギー源にはなりえない。
次に電力供給についてみてみる。今後、組み立て加工型産業の電力需要の増大に加えて、農村から都市への人口流入が進むとともに都市型生活が普及し、家庭の電力利用が増える。このため、電力需要が引き続き高い伸びで増大することは避けられない。需要想定では年率8%とみられている。電力化率はまだまだ低く、これまでも発電量が需要に追い付かない状況が続いており電力不足は当分解消されないだろう。現在、総発電量のうちの80%が石炭火力で、発電及び熱供給で使用される石炭は中国の総総石炭消費量の30%を占める。需要増があまりにも急ピッチで、工期が長い水力発電所の建設では追い付かず、ここでも石炭火力に頼らざるを得ない。
電源設備の開発計画では、発電電力量の75%を石炭火力で20%強を水力で、他を原子力発電・石油及びガス火力により賄うとされている。2000年では92年の約2倍の発電量1兆5000億kWhが、さらに2010年では2000年の倍、3兆kWhの発電量が必要と予想されている。発電設備容量でみると、2000・2010年の石炭火力設備容量は、115百万kW(1992年)からそれぞれ230百万kW・460百万kWの規模を確保しなければならない。1基百万kWの大型石炭火力発電所を毎年20箇所以上、次々と建設することになるが、これらが運転を始めると大量の石炭が消費されることになる。
こうしてみると、今後とも中国が石炭に依存しなければことは明らかである。需要を支える一次エネルギー供給は引き続き石炭が中心にならざるをえない。石炭生産量は1994年で12億3990万トン、2010年にはほぼ倍の20億トン前後の生産が必要で、年率3%強で供給し続けなければならない。
4.中国における石炭利用の課題
石炭の大量使用は、二酸化炭素CO2と酸化硫黄物Soxの排出、大量の煤塵・石炭灰発生を伴い、環境汚染を招きやすい。どのようなエネルギーを使うにせよ、環境保全に対する相応のコストは免れないが、中国の石炭利用についてはとりわけ課題が多い。
まず、中国で利用される石炭は、硫黄含有分が多いため、硫黄酸化物の発生量が相対的に多いという問題がある。その他アジアでの硫黄含有分0.5〜0.7%に比べて、中国で消費される石炭は平均1.3%と約2倍の硫黄分を含んでいる。炭田により異なるが、巨大な石炭鉱床を有する四川省や貴州・雲南省などの石炭は、3%ととりわけ高い。
次に、原炭から製品としての精炭を選別する工程にも課題がある。選炭作業における一工程として石炭を水で洗浄する洗炭が行われ、不純物や不良炭の除去を行うのが通常である。洗炭は脱硫効果があり、燃焼後の石炭灰も減少させる。また選炭作業によって容積が減少するため輸送量を減らすことができる。洗炭のためには大量の水が必要であるが、ほとんどの産炭地が水不足で洗炭水の確保が難しいという制約に加え、選炭工場から出る排水の処理にも多額の設備投資が必要である。さらに、洗浄済みの石炭は未洗炭に比べ価格が高いため、産業部門や一般家庭など最終需要者が環境対策面から洗浄済み石炭を選ぶことは採算上まずありえない。このような事情もあり、洗炭率は現在20%程度に留まっている。上記の理由から、今後石炭洗浄が飛躍的に進むことは期待できそうもない。
石炭生産の半分は中央政府が管理する炭坑から、他の半分は地方政府が所有している炭坑から生産されている。地方政府が所有する炭坑は1980年代の増産期に乱開発されたものが多く、ほとんどが小規模な炭坑であり、高度な選炭設備を設置する資力がない。また炭坑の保安面・安全性にも問題があり、冒頭で述べたような炭坑火災が起こる背景ともなっている。
以上は生産における課題であるが、石炭を消費地に送る輸送段階でもボトルネックがある。石炭供給を支える主要産炭地は、山西省 ・河南省 ・黒龍江省・四川省 ・河北省などの内陸部であるのに対して、需要が伸びる消費地は沿海地域であり、需給の地域アンバランスが極めて大きい。このため、石炭輸送がかける鉄道への負荷はひじょうに大きくなっている。一時期、新線建設が後回しにされたこともあり、鉄道輸送能力には遅れが目立つ。このような状況で、鉄道貨物輸送量に占める石炭の割合は全国平均で40%を越えており、北部地域では60%にも達している。生産された石炭が産炭地で積まれているいるといった例も少なくないという。輸送能力にボトルネックがあり、今後の沿海消費地における急速な石炭需要増を考えると、地域需給の不均衡は解消し難い。
さらに石炭消費においては、小規模で旧式の設備をもつ工場・事業所が無数にあり、極めて非効率なボイラーを使用している。効率のよい集塵装置や脱硫・脱硝装置はほとんど設置されていないため、中小規模工場では煤煙や二酸化硫黄 ・二酸化窒素がほとんど処理されないまま、大気中に排出されている。一般家庭でも暖房 ・厨房用として石炭が利用され、これは石炭総消費量の10%強にあたる。
国内石炭消費の30%を占める発電部門においても、中小規模の発電設備が多く、全体的にエネルギー原単位・熱効率が低く、また電力総合損失率が高い。つまり同じ1kWhを発電するために無駄に多くの石炭を使っていることになる。大半の発電所では煤塵対策として旧式の集塵器は設置しているものの、排煙脱硫および排煙脱硝装置は設置されていない。良質な石炭は鉄鋼業や輸出用に回されるため、電力用は硫黄含有率1%以上のものが使用されており、電力業から排出される二酸化硫黄は全国の30%を占めている。
以上のように、石炭生産→輸送→利用のいずれの段階においても、インフラ整備の遅れと利用効率の悪さが目立つ。石炭依存の下で、良質とはいえない大量の石炭が十分洗選炭されず、燃焼効率の悪いボイラーで脱硫装置もなく燃焼されているのが、現状である。
このため現在でも、二酸化硫黄や煤塵による大気汚染が著しい。世界保健機構(WHO)の二酸化硫黄濃度に関する大気質ガイドライン150 を超えた1年間の日数で比べると、アジア主要都市の中で中国が極めて高いと報告されている(アジア太平洋経済社会委員会ESCAP報告1993年)。貴陽 ・重慶 ・太原などの二酸化硫黄濃度はとりわけが高く、年平均で各々463, 351, 303 であり(1993年中国統計年鑑)、「いかなる年においても測定値の日平均濃度が超えてはならない限界値100 」という中国の環境基準を優に上回っている。冬季は暖房用に石炭が利用され、また大気の拡散が悪くなるため、これらの数倍になる。単位面積当たり硫黄酸化物排出量でみても、高排出地域が北京・天津から河北 ・山東 ・江蘇省の沿海地域へ、また山北 ・陝西 ・四川省の内陸部へ広がっている。硫黄酸化物は、呼吸器に悪影響を及ぼし四日市ぜんそくなどの公害の主原因となる物質であり、また酸性雨の原因ともなる。中国では酸性土壌が広がる南部地域、なかでも貴陽 ・重慶、湖南省で酸性雨が観測されている。
相応の環境保全対策が打たれないと、環境へ多大な負荷をかけ易いエネルギー利用構造になっており、効率のよい安定的なエネルギー供給システムが連動して構築されることが成長の条件であり環境保全の前提であるといえる。
5.資金の不足、技術の不足、認識の不足
中国では、1979年に環境保護法が試行されて以降、1980年代に様々な法体系と環境行政機構の整備が進められ、1989年、環境保全の基本となる「環境保護法」が制定された。環境影響評価制度・三同時制度・汚染物質排出費徴収制度および責任・登記許可証制度など8つの制度から構成されている。三同時制度は、「いかなる建設事業においても汚染防止及び管理のための施設が主体工事と同時に設計され、施工され、操業される」という規定で、事業に伴う環境汚染を未然に防止するための原則であり、1979年施行法当初から盛られている基本的考え方である。
法制度が整備され、実際面での適用とその効果が期待されるが、高額な公害防止設備を設置する投資インセンティブは、現段階では未だ収益が優先する一般企業でなかなか持ちえないのが現実である。ましてや小企業には手が出るものではなく、むしろ老朽化設備を更新する資金がない状況である。排汚費徴収制度も、徴収された財源の80%を企業に還元し、公害防止設備を整備させていく政策資金供給として、あるいは企業の設備投資資金を環境保全投資へ再配分する政策手段として機能してはいるが、企業は排汚費をコストに計上することが許されていることもあって、必ずしも企業経営の中で公害防止や環境保全の意識を高めるものには至っていない。
中国にとって、所得水準の向上そのための経済成長は、6,500万人もの絶対貧困層を抱え13億人にも迫る人口を有するが故に必須の政策課題である。広大な国土の上に13億人の人々が毎年相応の付加価値を生産し続けるには、まだまだ社会基盤の建設が必要であり、鉄・セメント・石油化学製品などエネルギー多消費産業が大量の資材を生産しなければならない。石炭依存のエネルギー供給構造の上に重化学工業偏重の経済が乗っているような産業構造の下で、経済成長が優先されるあまり環境保全が後手に回ると、取り返しのつかない結果を招きかねない。大規模炭田火災は、これを示唆する例である。
現在とこれからの状況を打開するためには、環境協力について、どのように考えればよいであろうか。大気中に排出される環境汚染物資の量を次のように4つの要因に分解して考えれば、状況と対策の軽重 ・難易がみえてくる。
環境汚染物質の排出量
= 生産拡大要因×産業構造要因×エネルギー原単位要因×(1−汚染物質除去率)
生産拡大要因は経済 ・生産の規模を表し、財サービスの生産規模が大きくなるほど排出量も多くなる。産業構造要因は、その経済が主にどのような財サービスを生産するかで、軽工業か重化学工業中心かによって排出量の大きさが変わる。エネルギー原単位要因は、たとえば鉄1トンを生産するために必要とされる様々な投入エネルギーの総量を表す。利用されるエネルギーの種類とその量は、鉄の製造方法や設備の効率・熱利用技術などによって異なってくる。汚染物質除去率は、利用された燃料が燃焼する際発生する環境汚染物質を環境保全機器や回収処理技術等により、どれだけ除去できるかという割合である。
前者2つは中国経済の動態そのものである。中国の人々が目標とする所得レベルの達成スピードが生産拡大要因を規定する。一国の産業構造は、資源賦与、消費生活の各レベルに応じた需要内容、技術蓄積、国際分業における位置付け等に依存し、中国経済の発展段階を表すものである。これらは、当事者の価値観と歴史的経緯が決める長期的な要因であって、中短期的に動かしうるものではない。
環境問題に対して具体的な対策を講じるばあい、まず突き当たる課題は、「資金の不足、技術の不足、認識の不足」である。第三者である日本が直接あるいは間接に支援 ・協力できることは、生産性向上と同時にエネルギー利用効率を引き上げるため、効率的な製造技術やエネルギー利用技術の提供、設備更新のための資金援助と、発生する汚染物質が排出される前に回収処理する技術と機器の導入促進に寄与することである。環境汚染物質排出量は、エネルギー原単位を下げ除去率を上げることによって、大幅に減少させることができる。日本には高度成長期に引き起こした公害の経験と環境保全対策、石油危機を乗り越えた省エネルギー対応の実績があり、中国ばかりでなく開発途上国からの期待は大きい。
政府開発援助のうち二国間援助の額でみると、日本から中国に対して1993年は13.5億ドル、94年では14.8億ドルの資金供与が行われており、中国は日本の海外経済協力対象国の中で第一位の援助受取国となっている。これまでも居住環境整備・公害対策及び省エネルギー対策・自然環境保全などの分野で、多くの対中国環境協力事業が進められている。今後とも、火力発電所や製鉄所など大規模生産設備の建設・更新、都市交通システム・下水道施設・廃棄物処理施設など社会インフラの整備においては、政府援助や民間投資など外資の導入がますます高まっていくと思われる。この中で効率的な生産技術とともに環境保全技術が順次、体系的に組み込まれていくことが望まれる。
エネルギー消費で日本の倍の規模を有する中国は、以上で述べたように今後の15年間でさらに2倍になる。資金制約や技術的基盤が不十分であるが故に、環境対策が後追いのまま石炭偏重の上で拡大が進めば、環境への負荷が蓄積され回復困難な影響が顕在化する可能性も否定できない。中国の環境保全及び省エネルギーに対して、政府間援助はもとより、地方自治体・民間レベルの幅広い国際協力と支援が長期にわたって必要と考える。
(以上)