Top Page > Online Resources > Energy & Environment / わが国のCO2削減対策、その評価と対応
産業とエネルギーの未来
わが国のCO2削減対策、その評価と対応
| II. わが国のCO2削減対策、その評価と対応 |
| 1. 2020年までの日本経済とエネルギー消費 |
| 1-1 日本経済の長期成長力 |
| 1-2 増大し続けるCO2排出量 |
| 2. CO2削減の政策代替シナリオ |
| 2-1 炭素税導入によるCO2削減効果と経済への影響 |
| 2-2 脱化石燃料、エネルギー代替によるCO2削減 |
| 3. 省エネルギー機器開発普及策の費用対効果 |
| 4. 結 論 |
U わが国のCO2削減対策、その評価と対応
CO2排出抑制のための環境税導入などが、経済成長にどの程度影響を与えるか、非化石燃料に対する依存をどの程度増やすべきか等を定量的に展望する。考えられるいくつかの選択肢の中で、どれが国民経済的に望ましいのか。モデル分析を踏まえ、ひとつの回答を示したい。
1.2020年までの日本経済とエネルギー消費
1-1日本経済の長期成長力
2000年から2010年まで総人口は1億2700万人でほぼ定常状態が続く。この期間、日本経済の構造改革が進み、情報通信ネットワークが経済を活性化させるなどにより年率1.8%の経済成長が可能となる。
2010年から2020年では、64歳以上人口が4人に1人を占め、高齢化指数が40%を越える社会に入る。労働力の逼迫と就業者平均年齢の上昇は労働生産性向上のための設備投資を促し、これらの投資が成長を支える。一方、高齢者の増加は消費総額の伸びを鈍化させ、また貯蓄性向の高い働き盛りの成年若年層のウェイトが下がり負担が増してくるため、消費支出増加のペースを緩めることとなり潜在成長力が弱まる。この期間の成長率は0.5%に低下し、以降、一人当りGNPは増加するものの(年率0.8%)、国内経済の規模としては緩やかに横這いの段階に入る。
図 1. 2020年までの日本経済
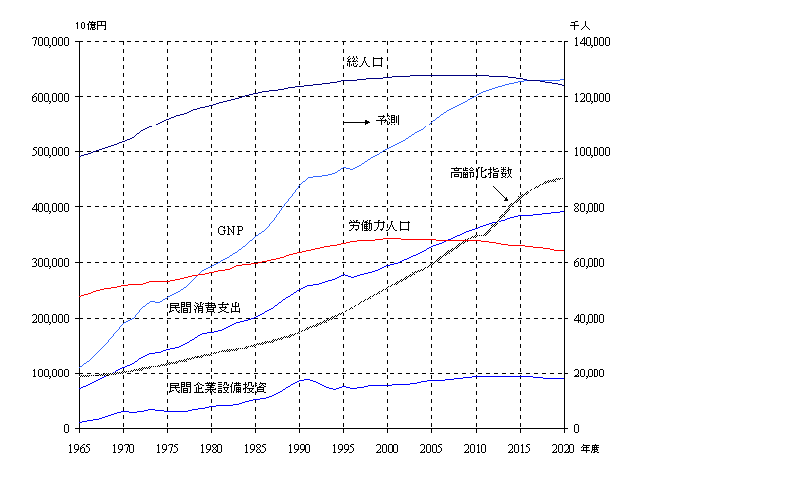
(出所)三菱総研作成
1-2 増大し続けるCO2排出量
一次エネルギー国内供給は、1995年現在5億2000万石油換算トン(toe)に達している。86年以降、GNP当りエネルギー利用効率の改善は進んでおらず、エネルギー消費は増加傾向にある。
エネルギー利用効率に大きな改善がみられず、これまでのトレンドでエネルギーが消費され続けたケースを考える。2000年から2020年までの実質経済成長率を、それぞれ1.8%(2010/2000年)、0.5%(2020/10年)とすると、一次エネルギー国内供給は、2010年まで年率1.3%で伸び、6億1100万石油換算トン(611 Mtoe)に達し、1990年466.3 Mtoeに対して1.3倍の消費水準となる。2010年以降、人口の減少・経済成長力の低下・産業構造の変化等により、その伸びは鈍化する。
一人当り一次エネルギー消費は、90年3.73 toe/人(95年4.15 toe/人)から2010年では4.79toe/人へ28%(対95年15%)増加する。
図 2. トレンド・ケース予測

(出所)三菱総研作成
一次エネルギー国内供給が伸び続けることから、CO2排出も増大し続け、2010年2020年とも4億炭素換算トンを越える量となる(2015年で4億1200万/t-C)。一人当りCO2排出量は、1990年2.59/t-Cから2010年3.18/t-C、2020年には3.26/t-Cへと増加する。
2度の石油危機に直面し、1975年から1985年まで素材産業を中心に大幅な省エネルギーが進んだ。当時、素材系の製造プロセスに改善の余地が多く、また並行して原子力発電への移行とエネルギー代替が急速に進展したことにより、1970年から1980年の10年間にGNP原単位を261toe/10億円下げることができた。
仮に、この期間に達成されたGNP当りエネルギー消費の改善が2000年以降にも実現できると想定すると(当時と同じ年平均で26toe/10億円の強力な省エネルギーが実現できれば)、2010年で1990年レベルのエネルギー消費とCO2排出量を同時に抑制することは、一応のところ可能である。→図20のA)
他方、1980年から1990年の省エネルギー進展度合いは、10年間で237toe/10億円、年平均にして23.7toe/10億円であったが、2000年以降このペースで進むとすると、1990年の消費レベルまで低下させるに至るのは2014年になる。→図20のB)
比較的穏やかといえる1.8%の経済成長を想定しても、現状のエネルギー消費を続けたばあい2010年のCO2排出量は4億炭素換算トンを越えると予想され、1990年6%削減目標レベル(約3億炭素換算トン)に対して、今後10年間に1億炭素換算トン強の削減が求められる。
産業部門における大幅な省エネルギー施策の目玉がないため、今回は、様々な分野で様々な施策の組み合わせでの(その意味ではコストのかかる)対応にならざるをえない。
以下では、CO2削減対策として現在議論されている「炭素税導入、原子力発電促進、市場を通じた省エネルギー機器開発普及助成」などが、削減目標達成のための十分な手だてとなりうるかどうか検討する。
2.CO2削減の政策代替シナリオ
2-1炭素税導入によるCO2削減効果と経済への影響
| 3,000円/炭素換算トンの比較的緩やかな炭素税導入は、経済への影響は少ないものの、CO2削減効果は小さい。 10,000円/炭素換算トンの炭素税では、税収を省エネルギー投資に振り向ければCO2削減効果を期待できる。 |
1)炭素税導入がもたらす効果、その影響
・エネルギー価格上昇によるエネルギー節約
・補助金・優遇税制等による省エネルギー投資促進
・助成を通じた省エネルギー技術の開発、省エネルギー機器の普及
・価格体系変化に伴う産業構造のシフト(サービス経済へのシフト)
・国内価格上昇に伴う可処分所得・法人所得の減少、国民総支出のDEPRESS効果
・エネルギー多消費産業の生産低下、製造業の国際競争力低下、海外LEAKAGE効果
2)低税率3,000円/t-C炭素税の効果と影響
課税対象: 炭素排出量に応じたエネルギー、生産輸入時点で課税
生産者が価格に上乗せし、最終消費者が税を負担する
税収の使途:省エネルギー投資促進、省エネルギー機器等の開発・普及のため、産業
あるいは消費者へ補助金として国内に還流
Simulation:2000年から3,000円/t-Cの炭素税を導入
炭素税収は約1兆円、一人当り1万円弱/年の負担
この低率課税で、使途を省エネルギー投資促進補助に特定化しない(たとえば一般財源、減税財源)ばあいは、最終エネルギー消費低減効果・CO2削減ともにほとんど効果がなく、それぞれ200万石油換算トン、200万炭素換算トンの削減に留まる。
図 3. 炭素税3,000円/t-C導入によるCO2削減効果
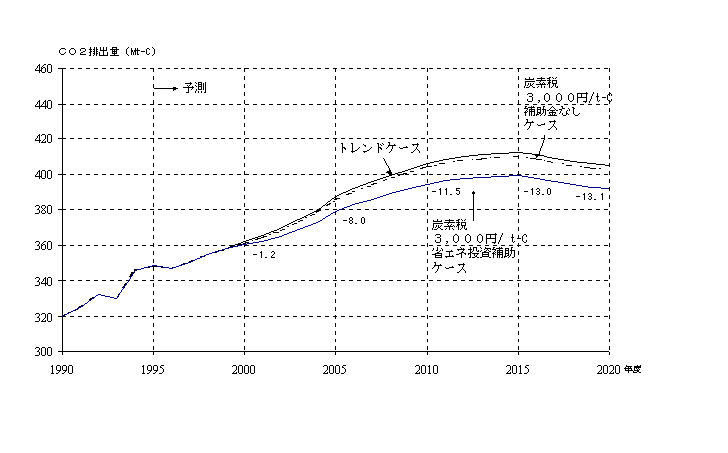
(出所)三菱総研作成
炭素税収総額は、名目GNP比0.2%程度、石油等の価格上昇は3%(ガソリン代にして数円)、電力1%、卸売物価の上昇は導入当初0.6%上と、経済への影響は少ない。税収が省エネルギー投資促進助成に利用されるケースでは、省エネ投資によりエネルギー消費原単位が徐々に低下するため、一次エネルギー国内供給を2010年で1400万toe、2020年で1600万toe押し下げる(トレンド予測ケースに対して、それぞれ2.3%、2.6%の減少)。
ただ2010年においても、そのCO2効果は1100万炭素換算トン程度で、国を挙げての環境対策への取り組みを示すアナウンスメント効果は十分に期待できるものの、低率3,000円/t-Cの炭素税では省エネルギー・省CO2の柱としては、いささか削減効果が弱い。
他方、1兆円の炭素税収を国内に還流するのではなく排出権取引に利用すると、1000万炭素換算トンの排出権を購入することができる(先進国間の取引価格を800ドル/t-Cと仮定)。これは、3,000円/t-C炭素税導入による国内でのCO2削減効果とほぼ同程度であるが、排出権取引では1兆円の所得が海外へ流出することになる。
表 1. 3,000円/t-C炭素税の効果と影響
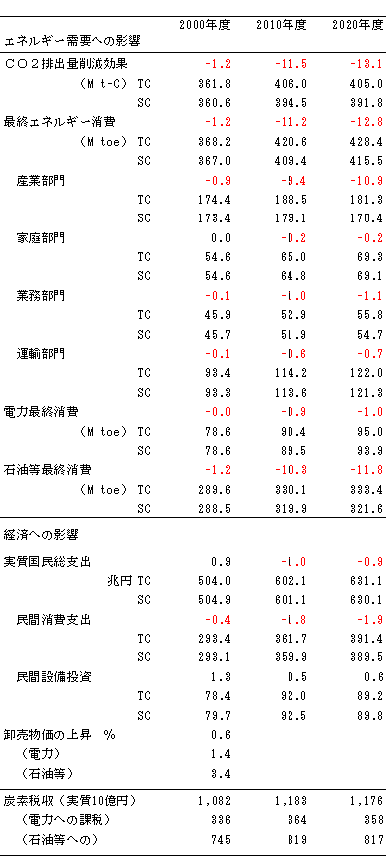
(出所)三菱総研作成 TCはトレンドケース、SCはシミュレーションケース
物価の上昇:導入年2000年における前年伸び
3)10,000円/t-C炭素税の効果と影響
Simulation:2000年から10,000円/t-Cの炭素税を課税、前提条件は上記ケースと同じ
炭素税収は3兆円、一人当り3万円/年の負担
経済への影響は、導入初年度、石油等の価格上昇が11%、電力4%強で、卸売物価を2%程度押し上げる。3,000円/t-C炭素税に比べ多少負担が大きいため、経済成長を2010年までの経済成長を年平均0.1%程度スローダウンさせる。
補助金なしのばあいでは、2010年で一次エネルギー国内供給900万toe減、600万炭素換算トンのCO2削減効果に留まる。
他方、省エネルギー投資促進助成を行うと、トレンド予測ケースに比して2010年で3400万toe、2020年で3700万toeだけ一次エネルギー国内供給を減少させ、2010年までの一次エネルギー国内供給の年率伸びを1.3%から0.75%へ0.5%ポイント引き下げる効果がある。また炭素排出量に応じて課税された税は石油等に厚くかかるため、電力需要の減少以上に石油等の最終エネルギー消費を抑制する。
CO2排出量削減は、2010年で2700万炭素換算トン、2020年では2900万炭素換算トンの効果を得る。ただ3,000円/t-C炭素税と比べると、省エネルギー投資の限界効率が低減してくるため、3倍の課税が必ずしも3倍のCO2削減効果を生み出すわけではない。
図 4. 炭素税10,000円/t-C導入によるCO2削減効果
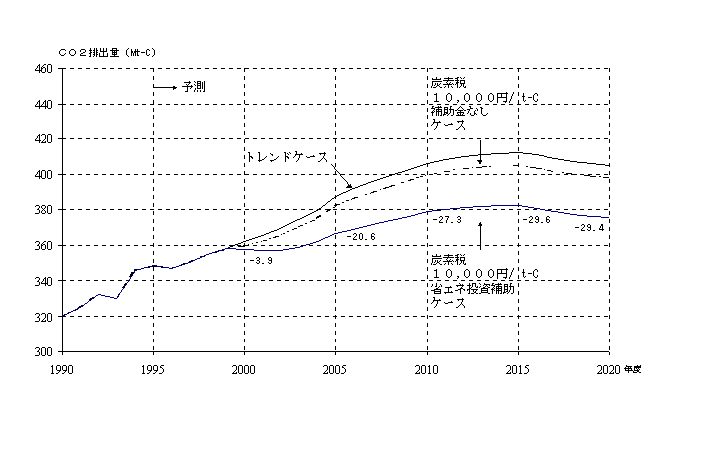
(出所)三菱総研作成
表 2. 10,000円/t-C炭素税の効果と影響
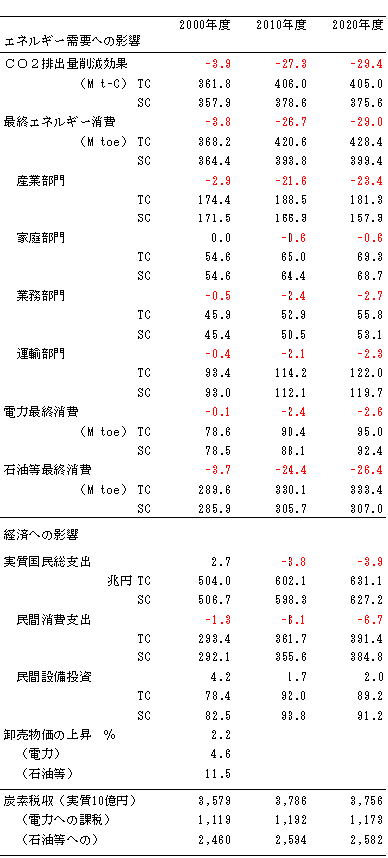
(出所)三菱総研作成 TCはトレンドケース、SCはシミュレーションケース
物価の上昇:導入年2000年における前年伸び
2-2脱化石燃料、エネルギー代替によるCO2削減
各種の新エネルギー開発が進めらているものの、2010年までに大幅なCO2削減が期待できる技術はいまのところ見つからない。そこで以下では、原子力発電がCO2削減策としてどれだけ期待できるかをみてみる。
| Simulation:原子力発電が促進される | |||||||
| 年度 | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | |
| 総発電量 | 億kWh | 8,573 | 9,899 | 10,050 | 12,200 | 12,800 | 13,050 |
| トレンドケース | |||||||
| 原子力設備容量 | 万kW | 3,164 | 4,136 | 4,650 | 5,580 | 6,4,90 | 7,540 |
| 原子力発電分担 | % | 23 | 29 | 31 | 32 | 35 | 41 |
| 原子力促進ケース | |||||||
| 原子力設備容量 | 万kW | 4,650 | 6,510 | 8,710 | 11,320 | ||
| 原子力発電分担 | % | 31 | 37 | 47 | 60 | ||
トレンドケースは、10年間でおおよそ1,000万kWずつ増加し2030年で7,500万kWの設備容量を想定した(これまでの実績は10年間で1,500万kW、政府見通しは2010年7,000万kWの原子力開発を目標としている)。原子力促進ケースでは、10年間に2,000万kWのペースで増加して2010年でおおよそ現在のフランスにおける発電設備容量を有し、2030年でフランス並みの発電分担率に近づくものとした。
現在のPA・新設立地の厳しい状況からすると急速なピッチでの建設が求められるが、これが実現したとして、原子力促進ケースにおけるCO2削減量は、2010年で約1,000万炭素換算トン、2020年では約2,200万トンとなる。
図 5. 原子力発電増によるCO2削減効果
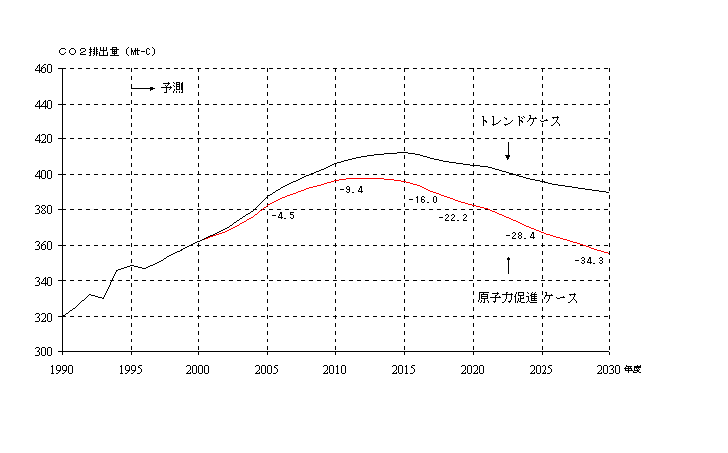
(出所)三菱総研作成
3.省エネルギー機器開発普及策の費用対効果
| 現在各分野で検討されている省エネルギー機器開発普及策は、最大限普及したとしても、期待できるCO2削減量は限られており、またそのコストも高い。 |
(1)代表的ないくつかの施策の省CO2効果とコスト・パフォーマンス
高気密住宅は冷暖房用エネルギーの節約により年間8kg-C/坪程度、ソーラーによる買電代替で180kg-C/年�・kW、ハイブリッド車では270kg-C/年�・台のCO2削減となる。また直噴ガソリンエンジン車200kg-C/年�・台、火力発電を高効率コンバインドサイクルに置き換えることで220kg-C/年�・kW、原子力発電の増設では1300kg-C/年�・kW。前者3つのCO2削減費用は、現在のところ後者の費用に比べて一桁高くつく。単純に経済性を比較すると、原子力発電が安い。
| CO2削減のための費用負担 | CO2削減最大期待量 | |
| (千円/炭素換算トン) | (万トン/年) | |
| 高気密住宅 | 250 | 720 |
| ソーラーシステム | 330 | 1,300 |
| ハイブリッド車 | 220 | 960 |
| 直噴ガソリンエンジン | 90 | 750 |
| 高効率コンバインドサイクル | 22 | |
| 原子力発電 | 16 |
(2)期待できる最大CO2削減量
極端な仮定だが、高気密住宅とソーラーが現在の一戸建て住宅全戸に普及したとして2,000万炭素換算トン、保有乗用車すべてをハイブリッドあるいは直噴車に置き換えても1,000万炭素換算トン。まとまったCO2削減量を得るためには相当の普及が必要であることが分かる。
その他様々な省エネ機器開発普及対策が検討されているが、いずれも普及率は総じて低く、またそれぞれCO2削減のための費用負担も大きい。普及に伴いコストは下がっていくにせよ、これらの対策の積み上げによってCO2削減を図るとすれば巨額の費用負担となる。
4.結 論
・日本経済は就業者の減少から2015年以降成長を鈍化させるものの、2015年までの成長ニーズは高い。
・一人当たりGNPの伸びは1.6%(2015/2000年)とある程度の生活向上は確保される。
・しかし、このばあいCO2排出は2010年・2020年とも4億炭素換算トンを越える量にならざるを得ない。
・機器の省エネルギー、社会システムの省エネルギーについては、現在考えられている対策では十分でなく、今後あらゆる分野で省エネ対策の新たなアイディアが出てくる必要がある。
・炭素税の効果は価格効果としては弱く、それを省エネ普及に使わない限り意味がない。
つまり、炭素税導入が大事なのではなく、省エネ投資を普及促進させることに意味がある。
現行エネルギー諸税の使途を省エネ促進型にするのも一策であろう。
・脱化石燃料化はやはり原子力に依存せざるをえない。CO2削減投資としてみたばあい、コスト・パーフォーマンスは高い。国としても削減策の柱として明確に原子力を位置づけ、開発を確実なものとしていく必要がある。
・現在普及が期待されている省エネ対策だけでは不十分であり、原子力開発が政府の期待どおりに促進され、かつ炭素税を財源として3兆円程度の省エネルギー投資助成をしたとしても削減目標に及ばない。
・2010年までのスパンでみると削減目標達成は非常に困難であり、国内対策を積極的に進めると同時に、排出権取引、クリーン開発メカニズム、共同実施などの有効的な活用も考えざるをえない。
(以上)